2022.01.26
ゆるむもふもふ!直径約15センチのこの“しっぽ”、誰の?【円山動物園さんぽ】

札幌市円山動物園は、ことし70周年を迎えました!これを記念したSitakkeの連載、「円山動物園さんぽ」。
長く愛されてきた背景には、一度だけでは味わい尽くせない、見どころの多さがあります。「さんぽ」するように気軽に通うことで見つけられる、動物たちの深~い魅力をお伝えしていきます。
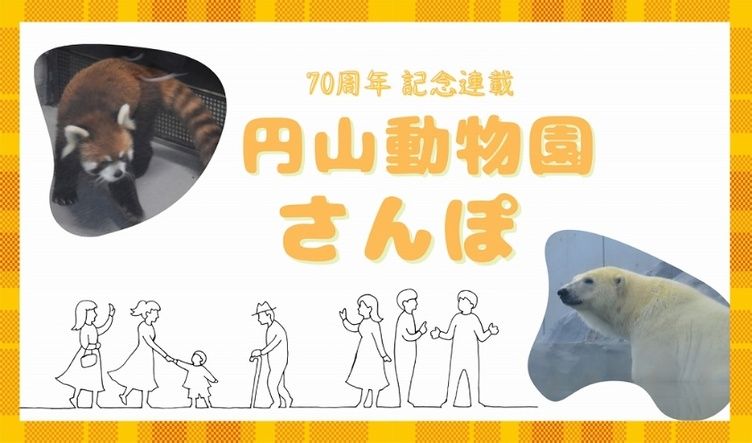
きょうご紹介するのは、冬になると、「しっぽ」が直径15センチほどの太さになるという動物。15センチは、千円札の横幅と同じくらい…!そんな“もふもふ”しっぽの持ち主は…。

「ユキヒョウ」です。しっぽは太いだけでなく、体長と同じくらいの長さがあります。この立派なしっぽにも、ユキヒョウの“冬の強さ”が詰まっています。
自分の倍以上の体重の獲物を…

ユキヒョウが住むのは、中央アジアの高山地帯。雪が降り、寒い場所です。円山動物園でも、野生に似せて、雪の間からゴツゴツとした岩が覗くような環境にしています。

高い岩場…この写真の中にユキヒョウがいるって、すぐにわかりましたか?

岩場の一番高いところで、おなかをべったり雪につけて、スヤスヤ寝ています。白と黒の模様が混ざり、グレーがかった毛は、この岩場で目立たない色になっているんだそう。

飼育員の工藤菜生(くどう・さい)さんは、ユキヒョウの担当を3年勤め、すっかり“ネコ派”になったそう。「ネコ科ならではの動きがユキヒョウの魅力のひとつ」と目を輝かせます。

目を細める表情は、まさに「ネコ科」
ユキヒョウの“獲物”は、大型のヤギやシカの仲間。ユキヒョウの体重は30~40キロほどですが、ときには100キロを超える獲物をしとめるといいます。その秘訣は、“山岳の狩り”を極めた「運動神経」と「知能」だそう。

狭い柵のフチ部分もスタスタと移動
体が大きいだけでなく、足の速い草食獣には、普通に追いかけても敵いません。しかしユキヒョウには、じぶんのテリトリーについて知り尽くした上での戦略があるのです。
獲物を見つけるとギリギリまで身を隠し、飛び出すときには「どこに追い込むか」を計算。ときには、崖に追い込んで、突き落としてからしとめるといいます。突き落とされた草食獣は弱る一方、ネコ科のユキヒョウにとっては、崖からケガをせずに飛び降りるのはお手の物です。

岩場を縦横無尽に動き回る「アクバル」
“登り”も得意。円山動物園のそびえ立つ岩場を登るのには、工藤さんは1分弱かかるのに対し、ユキヒョウのオス・「アクバル」は1秒で山頂に着くそう。ただ…ほぼ90度にそびえ立つ、足場の悪い岩場…工藤さんの1分弱も、相当早いです…。
しっぽも、おなかも、もっふもふ

“山岳の狩り”を支えるのが、立派な「しっぽ」の役割の一つ。登り降りのバランスをとるのに役立っています。工藤さんによると、冬は夏の2倍ほどの太さで、直径15センチほどになっているそう!この季節こそ、注目してほしいポイントです。
冬は「しっぽ」だけでなく、おなかの毛も12センチほどの長さに!麻酔をかけるために吹き矢を飛ばしても、はじき返されてしまうほどの毛の密度だそうです。

下から見上げると、白くてフワフワのおなかの毛が…
円山動物園では、体に負担をかけないために、できるだけ麻酔を使わずに採血などをしているといいます。オリの隙間から、しっぽを出してもらう練習をしているといいますが、「アクバルはエサが大好き」で、すぐにできるようになったそうです。凛々しい顔して、食いしん坊な一面もあるなんて、それも魅力的…。

アクバル、雪をペロリ
一方、透き通った目が素敵なメスの「シジム」は、音に敏感で慎重なタイプだそうです。

車の音に気付き、遠くを見つめるシジム
飼い猫のことも、どれだけ“生態”を知ってる?

円山動物園では、岩場だけでなく、植物も生息地に近いものにしているそう。それはユキヒョウにとっての過ごしやすさだけでなく、見ている人に「ユキヒョウの本来の暮らしをイメージしてほしい」からだといいます。

工藤さんは、「カラスやスズメ、家で飼っている犬や猫…身近にいる動物でも、生態を説明できないことって多いと思うんですよね。ユキヒョウも生息数が減っている中で、知ることが守ることの一歩。まじまじと見て、知って、『フカフカだな』『運動神経すごいな』…と、ユキヒョウに魅了されていってもらえれば」と話します。

シジムと見つめ合う工藤さん
寒い地帯で暮らすユキヒョウは、冬こそ活発な姿を見るチャンス。動きの速さや滑らかさ、冬毛のボリューム、毛の模様や姿勢、目の美しさ…。その姿は暖かい屋内から見ることもできるので、ゆっくり見つめて、“あなたが思うユキヒョウの魅力”を見つけてみてはいかがでしょうか。

過去記事一覧: 円山動物園さんぽ
この記事のキーワードはこちら
編集部ひと押し
あなたへおすすめ
Partner Media
パートナーメディア
