2025.07.14
暮らす「クマ鈴は効かない?」専門家が回答 気を付けるべき『危険な兆候』と、地域住民だからこそできること
クマ出没を「じぶんごと」にするとはどういうことか
有賀さんに続いてマイクを持った、北海道大学大学院の伊藤泰幹(いとう・たいき)さんは、4月と6月の出没を地域住民が予測できていたと、驚きの発表をしました。

2025年1月
伊藤さんは1月に、円山西町でワークショップを企画。地域住民がグループに分かれ、自分たちはどこでどんなクマ対策を求めているのか、地図を広げながら話し合いました。
まず過去の出没地点を書き込み、次に「クマの目線」から、出没の原因になるものを探します。

2025年1月
「クルミ」「農作物」などクマの食べものになるものがある場所、「草やぶ」などクマの通り道になる場所にシールを貼ったり、マーカーで書き込んだりしました。
4月と6月の出没場所は、この1月のワークショップで「クマが出るリスクがありそう」と話していたエリアと重なっていたのです。
川沿いや背の高い草やぶを移動するクマの習性を知っていることに加え、どこに草が生い茂っていて、どこに何の実がなっているかなど、地域住民だからこそわかる視点が入ると、対策が必要な場所は考えられるということが証明されたと言えます。
ワークショップでは、最後に「人目線」で、通学路やバス停など、クマに絶対に出てほしくない場所を話し合っていました。
「クマ目線」と「人目線」をかけ合わせることで、対策が必要な場所や、地域住民がどこでどんな対策を望んでいるのかが見えてきます。
町内会のメンバーは、このワークショップの後、クマ対策になる頑丈なごみ箱の視察に行くなど、実際に対策を考える次の一歩に進んでいます。
伊藤さんは今回の勉強会で、このワークショップの成果を振り返り、「クマ出没を『じぶんごと』にする、というのは簡単に言われますが、では『じぶんごと』にするとは何なのかを考えてみました。クマが出たらしいと漠然とした不安を抱えるのではなくて、やることや課題を具体化していくことが『じぶんごと』なのではないかと思います」と話しました。
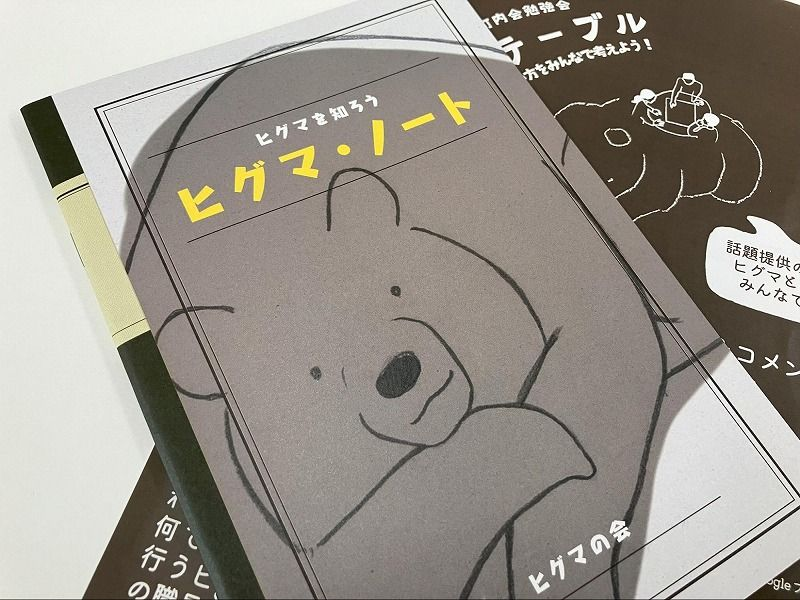
ヒグマについての基礎知識が詰まった「ヒグマ・ノート」(ヒグマの会発行)も配布された
この日、集まったのは約40人。満席の会場で、全員が真剣に有賀さんや伊藤さんの話に耳を傾けていました。その頼もしい姿は、「クマに強いまちづくり」が着実に進んでいることを物語っていました。
■ 『北海道ソフトクリームラリー2025』171店舗が参加!とろけるしあわせ巡りで豪華賞品が当たるかも?
■【4選】20年以上親しまれる名物ソフトも!小樽市で注目のソフトクリームを、地元編集部がピックアップ! #北海道ソフトクリームラリー2025
この記事のキーワードはこちら
編集部ひと押し
あなたへおすすめ
Partner Media
パートナーメディア
